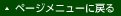口の中の病気
口内炎
尾側粘膜や頬粘膜に強い炎症が起こる病気です。
多くは猫の尾側口内炎を指すことが多いですが、犬も歯の表面のプラークにより頬などの粘膜に激しい炎症を起こす接触性口内炎という病態もあります。
猫の口内炎については詳細な原因は解明されておりませんが、何らかの細菌やウイルスが関与している可能性が考えられています。
犬も猫も重症化すると激しく痛がり、食事量も減少し、生活の質が顕著に落ちることもあります。
治療としては抗生剤やステロイドで一時的に軽減することはありますが、根本解決となると抜歯が必要になるケースも多いです。
猫ちゃんは1歳で発症する子もいますので、口周りを気にするなどの症状があれば動物病院を受診しましょう。
破折
破折
犬は硬いおやつ(鹿の角、ヒヅメ、骨、ヒマラヤンチーズなど)や硬いおもちゃを噛んだときに歯が折れたり、欠けたり、ヒビが入ることがあります。これを破折と言います。
中でも歯の中の神経が露出するほど大きく割れた場合、細菌が入り込み炎症を引き起したり(歯髄炎)、歯根部分に膿瘍をつくり顔が腫れたり周囲の骨が溶けたりします(歯根膿瘍)。
治療としては根管治療と抜歯が主にあげられます。
根管治療
全身麻酔をかけて、感染した歯髄を除去し、洗浄し、人工物を詰め、割れた部分はコンポジットレジンと呼ばれる強固なプラスチック素材などで修復します。
メリットは歯の機能を維持することができます。
デメリットは処置後半年や1年で2,3回麻酔/鎮静で歯科レントゲンによる評価が必要になります。
抜歯
細菌感染した歯を根本的に取り除くという治療になります。
メリットは基本的には一回の麻酔処置で完結すること。
デメリットは折れた歯やその子の噛み合わせにもよりますが、フードやおやつが噛みづらくなるなど歯の機能を失うことです。
根管治療も抜歯も正しい治療ですが、折れた歯、犬猫の噛み合わせ、年齢、食生活、全身麻酔のリスクなど様々な背景を考慮しオーナー様と相談した上で治療法を選択しています。
いずれにせよ、早期対応が必要になりますので歯が折れてそう、最近噛みづらそうなど気になる症状があればいつでもご相談ください。
歯周病
歯周病とは
歯周病は歯肉やなどの歯を支えている周りの構造が異常をきたす病気です。
歯垢や歯石が原因となり、歯肉に炎症が起こることで病気が進行します。
歯垢は歯の表面にくっついている細菌の塊です。歯垢が石のように固まってしまったものが歯石です。
歯周病がひどくなると歯肉が腫れ、出血したり、歯がぐらぐらして抜け落ちそうになってしまい痛みがでてます。
またお口の中の細菌が血液の中に入り体中を巡ることで様々な病気を引き起こすことも指摘されています。
歯周病がひどくなると

歯周病がひどくなり歯の根元まで細菌感染が進んでしまうと、歯の根の部分に膿が溜まります(根尖膿瘍)。
進行すると頬や顎が腫れてそこから膿が出てしまったり、顎の骨にまで炎症が及ぶと骨がもろくなり顎の骨の骨折をしてしまうこともあります。
状況により歯石の除去やお薬、抜歯などの治療が必要です。
普段からのデンタルケアは歯垢を取り除き、歯周病の予防にとても大切です。
上の写真は歯石が重度についてしまい、歯肉炎が起こり歯肉も痩せてしまっている状態です。